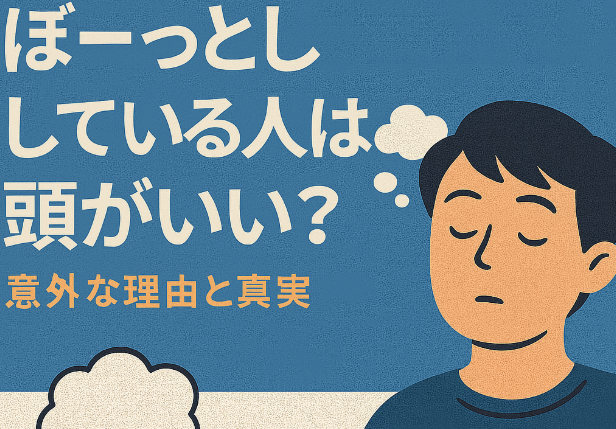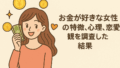一見ぼーっとしているように見える人が、実は頭の回転が速かったり、想像力や集中力に優れているという内容が多く見られます。脳の省エネモードや創造性といった科学的観点からも説明されており、「ぼーっとしている=怠け者」ではなく、「賢さの一形態」として紹介されています。
この記事では、脳科学や心理の観点から、なぜ「ぼーっとしてる人」が賢いのかを徹底解説!
「静かな人ほど頭がいい」と言われる理由や、「空想癖」がある人に共通する才能、さらには「マルチタスクが苦手でもOK」な裏づけまで、あらゆる角度からご紹介します。
\毎日更新!日替わりでお得/ 楽天ランキングページ24時間限定タイムセールはこちら<PR>
ぼーっとしてる人の特徴とは?
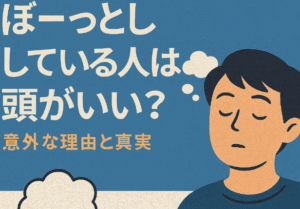
「ぼーっとしてる人」というと、反応が遅かったり、集中力がなさそうだったりと、どこかマイナスなイメージを持たれがちです。しかし、実際はそういった人たちの中に、非常に頭の回転が速く、深い思考をしている人が多いというのはあまり知られていません。外側が静かであるほど、内側の思考は活発に動いているということもあるのです。
彼らの特徴は、情報をすぐにアウトプットしないこと。周囲からの刺激を一旦すべて受け入れて、自分の中でじっくりと整理し、それから自分の言葉で発信する傾向があります。結果的に、「考えてなかったの?」と思われるかもしれませんが、実際には“言葉にする前の準備時間”が長いだけなんです。
たとえば、会議やグループディスカッションで、最初はあまり発言せず、黙っている人っていますよね。でも終盤に入ってから、「なるほど」と思わせる意見を言ったり、皆が見落としていた視点を提示することがありませんか? これは、瞬発力よりも思考の深さを優先している証拠とも言えます。
また、ぼーっとしている人は、視野が広く、細かい変化にも気づきやすい特徴があります。たとえば、職場で「今日、Aさんちょっと元気なさそう」と気づいたり、空気の微妙な変化を読み取るのが得意です。これは、表面だけでなく“全体”を見る力に長けているからこそ。
見た目の印象に騙されず、その静けさの中にどんな思考が流れているかを見抜くと、ぼーっとしている人の本当の魅力が見えてきます。実は、物事を深く洞察し、周囲を冷静に観察している賢い人なのかもしれません。
天才タイプの共通点
「天才肌」と言われる人には、見た目や行動がちょっと普通とは違う特徴があります。その中でも特に多く見られるのが、“一見ぼーっとしているように見える”こと。頭の中では複雑な思考を巡らせていても、それを外に出す必要を感じていないから、あまり表情やリアクションに現れないのです。
天才タイプの共通点としては、以下のようなものが挙げられます。
-
表面的な雑談にはあまり興味を示さない
-
一人で過ごす時間を大切にする
-
他人の感情に敏感で、空気を読むのが上手
-
「なぜ?」という疑問を深く掘り下げるクセがある
たとえば、スティーブ・ジョブズも幼少期から空想癖が強く、授業中も考えごとばかりしていたそうです。でも彼は、周囲と同じことをしない代わりに、独自の価値観を持ち、新しいものを創造する力に長けていました。つまり、「ぼーっとしているように見える人」は、表面的には受け身でも、内面では非常に能動的な活動をしていることがあるのです。
また、こうした人は“考えが深い”という共通点もあります。すぐに意見を言わない代わりに、一度考えたことは筋が通っていて、論理的な説明ができる人が多いです。その分、誤解されたり「何を考えてるか分からない」と思われがちですが、本質的には他者とのコミュニケーションより、自分自身との対話を大切にしています。
世の中の「成功者」と呼ばれる人の中には、子どもの頃に“変わり者”と思われていた人も少なくありません。その変わり者っぽさの中に、自分だけの世界を持ち、そこに集中できる力があるからこそ、天才的なひらめきや突破力が生まれるのです。
頭がいい人が空想にふける理由
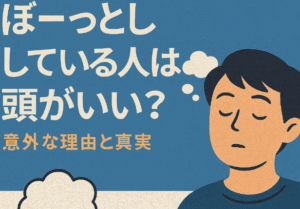
空想する時間は無駄に見えるかもしれませんが、実は脳の活動としてはとても重要なプロセスです。特にクリエイティブな発想が必要な場面では、空想の時間が「ひらめき」の種を生み出してくれることがあります。
空想にふけっているとき、脳は「デフォルトモード・ネットワーク(DMN)」と呼ばれる回路を活性化させています。これは、意識的に考えるのではなく、無意識的に記憶や経験、感情を組み合わせる働きをするもので、直感的なひらめきや創造的な思考と深く関わっています。
たとえば、電車の窓から外をぼんやり眺めていたときに、急に仕事のアイデアが浮かんだ経験はありませんか? これは、空想により脳が情報を再編成しているからです。意識的に考え続けても出なかった答えが、ふとした瞬間に「降りてくる」のは、DMNが働いている証拠なんです。
また、空想癖がある人は、他者の立場や感情を想像する「共感力」にも優れていると言われています。小説家や映画監督に空想好きが多いのもそのため。頭の中で場面や感情を描くことが得意だからこそ、リアルな物語を創り出せるのです。
社会的には「集中していない」「仕事していない」と誤解されやすいですが、実際には“集中の種類”が違うだけ。空想は、意図的な集中ではなく、自由で柔軟な集中なのです。
ぼーっとすることに罪悪感を持たず、むしろ「今、自分は情報を整理している最中」と捉えることで、その時間をより有意義なものにできるかもしれませんね。
脳の省エネモードとは
私たちの脳は、実はとてもエネルギーを使う器官。全身のエネルギーのうち、約20〜25%を脳だけで消費していると言われています。そんな脳がフル稼働を続けるのは負担が大きく、無意識のうちに「省エネモード」に切り替わることがあります。これが、ぼーっとしているように見える瞬間なのです。
脳の省エネモードとは、外部からの刺激に反応することを一時的に抑え、内部の思考や記憶の整理、情報の定着を優先して行う状態を指します。これは脳が疲れを感じていたり、エネルギーを節約しようとしているサインとも言えます。
たとえば、長時間の会議や授業で、ふと集中力が切れて頭がぼーっとしてくる瞬間、誰にでもありますよね。それは、脳がこれ以上外部情報を処理するのが難しいと判断し、自らエネルギーを抑えているからです。ただしこの状態は、「何もしていない」のではなく、「内面の整理をしている」と考えた方が正確です。
また、創造的な発想やアイデアが生まれやすいのもこの省エネモードの時。脳が一見休んでいるように見えるときこそ、過去の経験や知識が無意識的に組み合わされ、新しい発見や気づきが生まれやすいのです。
つまり、「ぼーっとしている=サボっている」と決めつけるのは大きな誤解。むしろ、意図的に省エネモードに入れる人は、自分のエネルギー配分を理解し、賢く使っていると言えます。人前では無口でも、裏では静かに思考を巡らせている。そんな人ほど、実は“頭がいい”タイプなのかもしれません。
注意散漫と集中力の違い
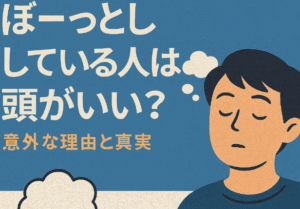
「ぼーっとしてる人って注意散漫じゃないの?」という疑問をよく聞きますが、実は“注意散漫”と“集中力が高い”ことは、共存することがあります。むしろ、一見注意力がなさそうに見える人ほど、特定のことに対してはものすごい集中力を発揮する場合があるんです。
注意散漫とは、注意の対象がコロコロ変わって一つのことに集中しにくい状態を指します。一方、集中力が高い人は、自分が興味を持ったことに対して強い“没頭力”を発揮します。これが「選択的集中力」です。つまり、集中する対象を自分で選んでいるということです。
たとえば、周囲の話し声が気になってしまうのに、自分が好きな小説を読み始めると周りの音が全く気にならなくなる、という人。これは決して注意散漫なのではなく、「何に集中すべきか」を脳が取捨選択しているのです。
子どもの頃、授業中はぼーっとしていたのに、自分の好きな絵やゲームになると信じられない集中力を見せていたという話もよくありますよね。これは典型的な「内向的集中型」の傾向。外からの情報を追うのが苦手でも、自分の世界に入ると驚くほどの集中力を発揮できるのです。
つまり、「ぼーっとしているから集中力がない」と決めつけるのは早計。人によって集中の仕方が違うだけであり、周囲の刺激に流されず“自分で集中をコントロールできる人”は、むしろ非常に賢いとも言えます。
無意識の情報処理
ぼーっとしている時間にも、私たちの脳は働き続けています。しかも、それは意識的に考えているときとは違う「無意識の情報処理」というかたちで行われているのです。この働きこそが、ぼーっとしている人が「頭がいい」と言われる理由の一つ。
無意識の情報処理とは、日々取り込んだ情報や経験、感情を、脳が裏側で勝手に整理・分析しているプロセスのことです。意識しなくても、脳内では「これは大事」「これは不要」といった選別が自動的に行われており、それがふとした瞬間の“ひらめき”や“勘”として現れるのです。
たとえば、ある課題にずっと悩んでいて、いったんそれを手放してリラックスしているときに突然答えが思い浮かぶことってありますよね。それは、意識の中では考えていなくても、脳の無意識領域で情報処理が続いていた結果なのです。
また、無意識の情報処理がうまく働く人は、感覚的に物事の全体像をつかむのが得意です。人の言葉の裏にある本音を感じ取ったり、場の空気の変化を察知する力にも優れています。こうした“直感力”も、実は無意識のデータベースが正確に働いているからこそ発揮されるものなんです。
つまり、ぼーっとしている時間こそが、脳にとっては非常に大切な「整理と再構築の時間」。無意識の情報処理をうまく使える人は、問題解決力や創造性の面でとても有利です。それを表には出さずに静かにこなしている人こそ、本当に頭のいい人なのかもしれませんね。
内向型と外向型の違い
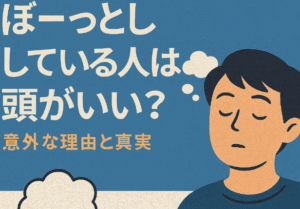
人の性格は大きく分けて「内向型」と「外向型」に分類されることが多いですが、「ぼーっとしてる人=内向型」という印象を持たれることがあります。確かにその傾向はあるものの、ここにはもっと深い違いと魅力があります。
外向型の人は、周囲との交流や刺激からエネルギーを得るタイプ。話すことで考えを整理し、人と関わることに楽しさを感じます。一方、内向型の人は、内面にエネルギー源があり、一人で過ごすことで思考を深め、リフレッシュします。
たとえば、外向型の人は飲み会などで盛り上がると元気になりますが、内向型の人は長時間の集団行動のあとに「どっと疲れる」というケースが多いです。これは決して人が嫌いなのではなく、脳の刺激に対する感受性が高く、情報を処理するための“静かな時間”が必要だからです。
内向型の人は、周囲から「おとなしい」「何考えてるかわからない」と思われがちですが、実際には頭の中で多くの会話や検討をしていることがよくあります。慎重に物事を捉え、深く考える力を持っているため、発言するときには核心を突くことが多いのも特徴です。
有名な内向型の人物には、ビル・ゲイツやオードリー・ヘプバーンなどがいます。彼らは社交的な場よりも、自分の専門分野や感性に集中することで成果を上げてきたタイプ。つまり、「ぼーっとしているように見える人」ほど、実は内向型であり、静かな思考力を秘めている賢い人であることが多いのです。
頭がいい人は一人の時間を好む人の思考
「一人の時間が好き」という人に対して、ネガティブな印象を持たれることがありますが、実際にはこのタイプの人こそ、思考力が高く、自分の世界を深く探求する力を持っていることが多いです。
一人でいる時間は、他人の意見や雑音から解放され、純粋に自分の考えと向き合える時間です。この“内省”の時間を大切にしている人ほど、冷静に物事を判断したり、複雑な問題を整理して理解する力に優れています。
たとえば、小説を書いている人やクリエイター、学者などは、一人の時間を好む傾向が強い職業です。彼らは静かな場所でじっくりと考え、独自の世界観やアイデアを育てていきます。これは、他人と一緒にいることで得られる刺激とは異なり、自分の内側から発想を引き出す力なのです。
また、一人の時間を楽しめる人は、感情の起伏も比較的安定しています。自分で自分の気持ちを整理する習慣があるため、突発的な感情に振り回されることが少なく、冷静で穏やかな印象を与えることも多いです。
「ぼーっとしている」と見られがちなこの時間は、実は頭の中でさまざまなシミュレーションが行われている時間。未来のこと、過去のこと、今気になっていることを整理しながら、自分なりの答えを出そうとしているのです。
このように、一人の時間を大切にする人は、自立心が強く、判断力があり、深い洞察力を備えた“静かな賢者”のような存在。表には出さなくても、確実に頭の中で世界をつくっているタイプなのです。
頭がいい人は頭の回転が速い!その行動
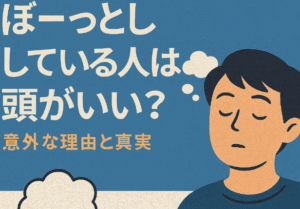
「この人、頭の回転が早いな」と感じる人には、ある共通する行動パターンがあります。そして意外にも、そういった人ほど“静かで控えめ”に見えることが多いのです。
頭の回転が速い人は、まずインプットのスピードが違います。話を聞きながら、情報の本質を瞬時に把握し、自分の中で論理的に整理していく力があります。そのため、会話のテンポに無理に合わせず、必要な時に的確な発言をすることができます。
たとえば、誰かが問題提起したとき、最初は黙って聞いているのに、数分後には「こういう視点もありますよ」とまったく別の角度から提案をしてくるような人。これは、単にアイデアを思いついたというより、状況全体を見渡して整理し、効率的な道を瞬時に計算している証拠です。
また、頭の回転が速い人は、“質問力”にも優れています。自分の理解を深めるために、相手に適切な質問を投げかけ、会話の質を高めるのです。このようなやり取りは、結果的にチーム全体の思考レベルを引き上げる役割も果たします。
一方で、回転が速すぎるあまり、相手に合わせることにストレスを感じたり、「なぜ分からないのか」が理解できず、無口になってしまう人も少なくありません。これは決して傲慢なのではなく、相手に配慮した結果、言葉を選んでいるだけなのです。
静かだけれど、確かな論理と思考力を持っている人。そういうタイプこそ、表には出さずとも頭の回転が速い“本物の賢さ”を持った人と言えるでしょう。
静かな人ほど賢い理由
「静かな人って、何を考えているかわからない…」と言われることがありますが、実はその“静けさ”こそが、賢さの現れであることが多いんです。なぜなら、静かな人は情報を内側でしっかり処理し、自分の言葉で考えをまとめるタイプだからです。
まず、静かな人は「話す前に考える」傾向が強く、思いつきでは発言しません。何かを発言する際も、その言葉の影響や意味、裏にある感情などをしっかりと吟味してから言葉にします。そのため、発言は少なくても内容には深みがあり、「なるほど」と思わせる力があります。
たとえば、グループディスカッションでみんながわいわい意見を出している中、ずっと黙っていた人が、最後に「それって○○ってことじゃないですか?」とシンプルにまとめる場面。こういう人は、他人の意見をすべて受け止め、頭の中で分類し、本質をすくい取る力を持っています。
また、静かな人は観察力が高く、空気や雰囲気の変化に敏感です。声高に自分を主張するよりも、周囲の状況を読みながら行動するため、冷静で的確な判断ができる場面も多いのです。
心理学では、「内省型知能」と呼ばれるタイプがこれにあたります。このタイプは、物事を深く掘り下げる力、自分の感情や考えに気づき、それを整理する能力に優れており、表面的な賢さではなく“本質的な知性”を持っているとされます。
つまり、静かな人ほど実は「よく考えている」ことが多く、その落ち着いた態度の中に知性が隠されているのです。声が大きくなくても、内容がある。それこそが、本当に頭のいい人の特徴なのかもしれません。
ぼーっとすることのメリット
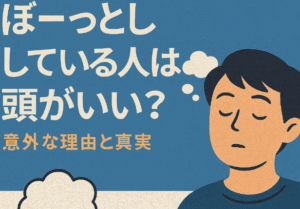
「ぼーっとしてしまった…」と罪悪感を抱く人も多いかもしれませんが、実はこの“ぼーっとする時間”には多くのメリットがあります。とくに、現代のように常に情報が流れ込む時代では、あえて脳を休める時間はとても大切です。
ぼーっとしているとき、脳は“休憩”しているように見えて、実は無意識に情報の整理をしています。これは「マインドワンダリング」と呼ばれる状態で、脳が自由に思考を漂わせているときに起こります。この時間に、過去の経験や知識が結びつき、新しい発想が生まれることも珍しくありません。
たとえば、シャワーを浴びているときや、寝る前にぼんやりしているときに、突然アイデアが降ってくることってありませんか? これは、脳が意識的な思考から離れて、より柔軟なモードに入ったことで、直感やひらめきが現れた証拠です。
また、ぼーっとする時間には、ストレスを軽減する効果もあります。脳がリラックスモードに入ることで、自律神経が整い、心が落ち着くのです。これによって集中力も回復し、次に取り組むべき作業にもスムーズに入れるようになります。
さらに、人間関係においても「ぼーっとする癖」がある人は、余計な発言をせず、冷静に周囲を見られるため、信頼されることが多いです。直感的に動くのではなく、一呼吸おいてから反応する姿勢は、賢い大人の態度としても評価されます。
ぼーっとすることは、決して「サボり」ではありません。それは、自分の脳を守り、整え、再び動き出すための“準備時間”なのです。心と頭にスペースを作ることで、より賢く、より柔軟に生きていく土台を築けるのです。
社会的誤解と本質
ぼーっとしている人に対して、社会的には「集中力がない」「怠けている」「要領が悪い」といった誤解がつきものです。でも、それは“表面的な印象”にすぎません。実際には、その人の中で複雑な思考や整理が行われていることが多く、表には見えないだけなのです。
現代社会は、常に行動し、発言し、成果を出すことが求められる“アウトプット社会”。だからこそ、静かにしている人や、反応が遅い人に対して「何もしていない」と判断されがちです。しかし、真の賢さは“内側でどれだけ深く考えているか”に表れます。
たとえば、学校で「反応が遅い」と言われていた子どもが、実はその分、人の気持ちを深く理解していたり、物事を筋道立てて考えるのが得意だったという話はよくあります。こうした子は「すぐに答えを出す」よりも「納得できる答えを出す」ことを大切にしているのです。
また、ビジネスの現場でも、“即レスより深レス”を重視する人が評価される場面があります。短時間で多くを発信する人が目立つ一方で、静かに聞いていて、的確にまとめる人が「頭がいい」と評価されることも珍しくありません。
このように、ぼーっとしているように見える人は、社会的な誤解を受けやすい存在ですが、その本質には深い知性や観察力、内省の力が隠れています。一見マイナスに思われる特徴も、視点を変えれば大きな強み。
今後は、「すぐに動けること」や「声が大きいこと」だけを基準にせず、「どんな思考をしているか」「どう整理しているか」にもっと目を向ける社会であってほしいですね。静けさの中にこそ、本質的な賢さが宿っているのです。
天才肌の人の見分け方
「この人、なんだか天才っぽい」と感じたことはありませんか? 天才肌の人は、一般的な“優秀さ”とは少し異なり、独特の感性や行動パターンを持っているのが特徴です。そのため、見た目や表面の態度だけでは判断しづらいですが、いくつかの共通点があります。
まず、天才肌の人は「他人と比べることに興味がない」ことが多いです。自分の価値基準をしっかり持っており、流行や周囲の評価に流されず、自分のペースで物事を進めます。だからこそ、「マイペース」「変わってる」と思われることも。
また、強い好奇心と集中力を併せ持っているのも特徴。興味のある分野には没頭し、時間も忘れて探求を続けます。たとえば、子どものころからひとつのことに熱中して周囲が見えなくなるようなタイプは、大人になってもその特性を活かしやすいです。
さらに、空気を読みすぎない・周囲に合わせすぎないという傾向もあります。協調性がないわけではありませんが、常に「これは本当に正しいか?」と自分なりに判断し、納得できる行動を選びます。この“自分軸”の強さが、常識にとらわれない発想やイノベーションに繋がるのです。
そして何より、天才肌の人は「観察眼」が鋭い。周囲の細かい変化や、人の言葉の裏にある意味に気づく力を持っています。それを声に出さずとも、自分の中で蓄積しており、必要なタイミングでそれを活かすことができるのです。
つまり、天才肌の人を見分けるには、“今見えている部分”よりも“見えない部分”に注目すること。ぼーっとしているように見えて、内側では常に考え、感じ、整理している。そんな人こそが、本当の意味で頭が良く、天才に近い存在なのかもしれません。
マルチタスクが苦手な理由

「頭の良い人って、なんでも器用にこなすイメージがある」そう思われがちですが、実は“マルチタスク”が苦手な賢い人は意外と多いんです。その理由は、思考の深さと集中力の質にあります。
マルチタスクとは、複数の作業を同時並行でこなすこと。しかし脳科学的には、人間の脳は“真の同時処理”ができるわけではなく、実際には“高速でタスクを切り替えているだけ”というのが実情です。この切り替えにはエネルギーが必要で、思考の深い人ほどこの切り替えにストレスを感じやすいのです。
たとえば、文章を書いている最中に電話が鳴り、それに応答した後また文章に戻ると、どこまで考えていたか忘れてしまう…こんな経験、ありますよね? これは、深く集中していたからこそ、“思考の断線”に弱いという証拠でもあります。
また、天才肌の人や深い思考をするタイプは、「一つのことをじっくり考え抜く」ことを好みます。ひとつのアイデアをさまざまな角度から検証し、納得いくまで掘り下げる。そのため、次々と違う作業に切り替えるマルチタスク的な働き方は、かえって非効率になってしまうのです。
マルチタスクが得意な人が「要領の良さ」を重視するタイプだとすれば、苦手な人は「質の高さ」や「本質的な理解」を重視するタイプ。どちらが優れているというよりも、使う脳のスタイルが異なるだけなのです。
ぼーっとしていても、一つのことに深く集中している人は、それだけで大きな力を発揮します。マルチタスクが苦手でも、それは「考えの深さ」がある証。そこにこそ、賢さの本質があるのです。
アイデアが浮かぶ瞬間
「いいアイデアが浮かばない…」そんなときほど、意外と“ぼーっとする時間”が大切だったりします。なぜなら、アイデアというのは無理やり考え込んで出すものではなく、“ふとした瞬間”にひらめくことが多いからです。
心理学や脳科学の分野でも、創造的なアイデアは「脳のリラックス状態」にあるときに生まれやすいとされています。これを「インキュベーション(孵化)効果」と呼び、問題を一旦頭の片隅に置いておくことで、無意識が情報を再構成し、答えを導き出すプロセスです。
たとえば、通勤中に音楽を聴いているとき、料理をしているとき、夜寝る前に布団に入った瞬間など、「考えていなかったのに思いついた!」という経験、ありますよね。これは、意識の力ではなく、無意識がうまく働いた証拠です。
ぼーっとしているとき、脳の“デフォルトモード・ネットワーク(DMN)”という回路が活発になり、創造力や記憶の整理が進む状態になります。このときこそ、ばらばらだった情報が結びつき、新しい発想が生まれやすくなるのです。
さらに、アイデアが浮かぶ瞬間には「余白」が必要です。常に何かに集中していたり、スケジュールで埋め尽くされた日々を送っていると、発想の余地が生まれません。だからこそ、散歩や昼寝、ただ空を見上げる時間がクリエイティブな種を育てる貴重な時間になるのです。
結局のところ、ひらめきとは、意図的に“ぼーっとする時間”を持てる人が受け取れるご褒美のようなもの。だから、「考えてない」ように見える人ほど、実は次のアイデアを静かに待っている、そんな賢い脳の使い方をしているのです。
ぼーっとしている人ほど“賢い”という真実まとめ
一見「何もしていない」ように見える“ぼーっとしている人”。
けれど、その静かな時間の中で行われているのは、実は高度な情報処理や深い内省。現代社会では見落とされがちですが、「静かに考える」「周囲に流されず思考を巡らせる」という行為は、知性のひとつの形なのです。
本記事を通してわかったのは――
ぼーっとしている=頭がいい可能性が高いということ。
ここで、具体的な理由と例をもう一度整理しておきましょう
ぼーっとしている人が「頭がいい」と言われる理由
-
脳の省エネモードをうまく活用している
→ 無駄なエネルギーを使わず、思考に集中する効率的な脳の使い方。 -
空想やひらめきが生まれやすい脳の状態
→ アイデアがふと降りてくるのは、思考を緩めたリラックス時。 -
無意識下での情報処理能力が高い
→ 表面的にはぼんやりして見えても、裏では脳がフル回転している。 -
深い集中力を発揮する“選択的集中”タイプ
→ 必要なときにだけ集中するため、効率的かつ的確な行動ができる。 -
内向型ならではの深い観察力と内省力
→ 表に出さず、言葉の裏側や空気の変化を察知して対応できる。 -
一人の時間を通して思考を整理している
→ 自己理解が深く、判断や発言に説得力がある。
こんな行動や特徴があれば「賢いぼーっとさん」かも?
-
周りが盛り上がっていても一歩引いて観察している
-
空を見ながら考えごとをしている時間が好き
-
会議で最後に核心を突く発言をする
-
小さいころから空想やひとり遊びが好きだった
-
人と話すより、考えごとをしている時間が落ち着く
-
何かに集中すると周囲の音が全く聞こえなくなる
「すぐに反応しない=劣っている」という思い込みは、これからの時代ではもう通用しないかもしれません。むしろ、内側に深い世界を持ち、自分のペースで考え、静かに行動する人こそ、これからの社会において大きな価値を発揮する存在です。
ぼーっとする時間を、自分を整えるための知的な“余白”として、大切にしてみてくださいね。
その中からきっと、あなただけの新しい発想や可能性が生まれてくるはずです。