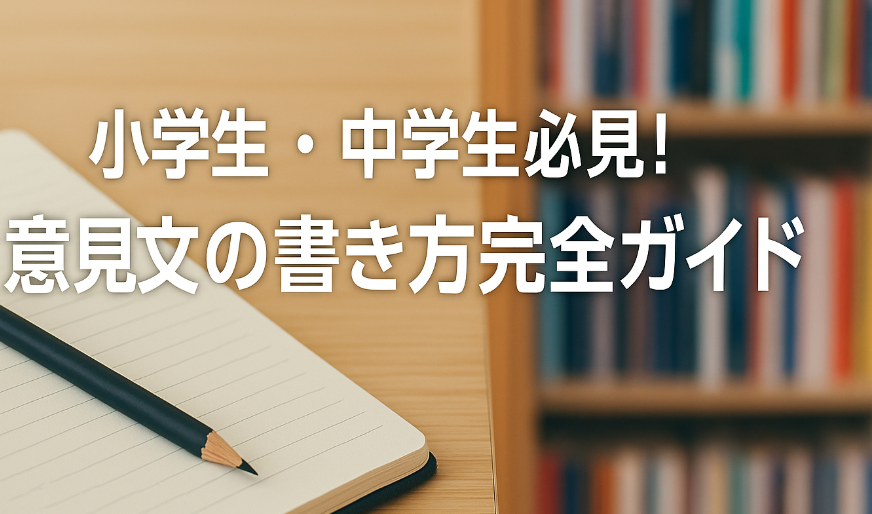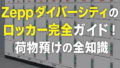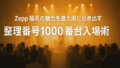この記事は、小学生や中学生、またはその保護者や先生に向けて書かれています。
「意見文の書き方 小学生 中学生向け」で検索した方が、意見文の基本から応用までしっかり理解できるよう、わかりやすく解説します。
意見文の構成や書き方のコツ、例文、よくある悩みの解決法まで、これ一つで意見文が得意になる完全ガイドです!
小学生・中学生向け意見文
意見文とは?その重要性について
意見文とは、自分の考えや主張を読み手にわかりやすく伝えるための文章のことです。
学校の授業や作文コンクールで書くことが多いですが、実は社会に出てからもとても役立つスキルです。
たとえば、授業中に「あなたはどう思いますか?」と聞かれたとき、頭の中では考えていても、うまく言葉にできないことがありますよね。
意見文を書く練習をすると、こうした場面で 「自分の考えを順番に整理して伝える力」 が育ちます。
また、入試の作文、将来の仕事での報告書、友だちや家族との話し合いなど、さまざまな場面で「意見を伝える力」が必要になります。
早いうちから慣れておくことで、大人になっても困らず、自信を持ってコミュニケーションができるようになります。
意見文を書くと身につく力
-
自分の考えを整理できる
-
相手にわかりやすく伝える力が育つ
-
将来のコミュニケーションに役立つ
-
考えを深めるクセが身につく
実際、ある中学生のAさんは「意見文の書き方」を練習したことで、授業で手を挙げて発表することが増えたそうです。
「順番に説明できる自信がついたから、前より話しやすくなった」と話していました。
このように、意見文は“書く力”だけでなく“話す力”も強くしてくれます。
意見文を書く目的と役割
意見文を書く大きな目的は、「自分の考えを明確にし、読み手に納得してもらうこと」です。
ただ感想を書く作文とはちがい、意見文では “なぜそう思うのか” を説明することがポイントになります。
たとえば「もっと読書の時間をふやすべきだと思う」という意見を述べるときも、
-
どうしてそう思ったのか
-
その理由を裏付ける体験はあるか
-
他の人にもわかってもらえる説明になっているか
こうした点を意識してまとめると、説得力のある意見文になります。
実際に、小学生のBくんは「給食の時間を長くしてほしい」というテーマで意見文を書きました。
理由として「落ち着いて食べられると、食べ物を残す人が減ると思う」という説明を入れ、さらに自分の体験として「急いで食べて気分が悪くなったことがある」と書きました。
このように 理由+体験 を入れると、読み手が「なるほど」と納得しやすくなります。
意見文の役割
-
自分の意見をはっきり伝える
-
読み手に理解・共感してもらう
-
論理的に考える練習になる
-
思考を整理する習慣が身につく
意見文の種類とその特徴
意見文にはいくつかのタイプがあり、目的や内容によって書き方のポイントが少しずつ変わります。
これを知っておくと、テーマに合わせて書きやすくなります。
主な意見文の種類
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 自由意見文 | 自分の好きなテーマで書く(例:読書、スポーツ、学校生活など) |
| 課題意見文 | 社会問題や課題について書く(例:いじめ、環境問題、食ロスなど) |
| 体験意見文 | 自分の体験をもとに意見を書く |
それぞれの具体例
● 自由意見文の例
「SNSの使い方について」「朝ごはんが大切だと思う理由」など、自分が興味のあるテーマならOK。
中学生Cさんは「部活動で学んだこと」をテーマにし、仲間との経験をもとに意見をまとめました。
● 課題意見文の例
「ポイ捨てをなくすためには」「学校のルールはどうあるべきか」など、社会的なテーマが多いです。
これは入試でもよく出る形式です。
● 体験意見文の例
「運動会の経験から感じたこと」「読書感想から考えた意見」など、自分の体験を説明と理由に使います。
身近な体験を元に書けるため、小学生にも書きやすいタイプです。
どのタイプの意見文でも、基本の流れは同じです。
主張 → 理由 → 具体例 → まとめ
この順番を意識するだけで、読みやすい意見文になりますよ。
意見文の基本構成
主語と述語の役割
意見文を書くときにまず大切なのが、「主語」と「述語」をはっきりさせることです。
主語とは、「だれが」「何が」の部分。
述語とは、「どうする」「どう思う」の部分です。
例えば、
×「図書室はとても良いと思います。」
→これだと、誰がそう思っているのか分かりません。
〇「私は、図書室はとても良い場所だと思います。」
→主語が入ることで、読み手にスッキリ伝わります。
小学生や中学生の場合、文章が長くなると主語と述語が離れてしまい、文の意味が分かりにくくなることがよくあります。
たとえば、作文コンクールむけに長い文章を書いた6年生の子が、「私は」と書いたあとに説明が続き、述語を忘れてしまった…ということも実際にありました。
そのため、
-
主語と述語はセットで考える
-
一文を長くしすぎない
-
「私は」「ぼくは」と主語を意識して入れる
この3つを心がけるだけで、文章がとても読みやすくなります。
結論の書き方
意見文では、文章の最初に「結論(自分の意見)」を書くのが基本です。
なぜなら、読み手が「この人は何を主張したいのか」を最初に理解できるからです。
たとえば、
-
私は、もっと読書の時間を増やすべきだと思います。
-
ぼくは、学校の休み時間は長い方がよいと考えています。
このように、はっきりした言い方にすると、読み手も読みやすくなります。
実際に、中学1年生のDさんは、意見文を書くときに結論を後回しにしてしまい、先生から「何を言いたいのか読み取れない」とコメントをもらってしまったそうです。
その後、「最初に結論」を意識して書くようにしたところ、文章の流れが自然になり、クラス内でも「わかりやすい!」と褒められるようになったとのことです。
また文章の最後にもう一度結論をまとめることで、読み手に強く印象づけることができます。
-
最初に結論を書く
-
「私は○○だと思います」と明確に言い切る
-
最後にも結論を書き、文章を引き締める
この流れを守るだけで、説得力がぐっと上がります。
本論の具体的な内容と構成
本論は、意見文の中心となる部分で、結論を支える理由や具体例を書きます。
読み手が納得できる文章にするためには、
-
理由を2つ以上書くこと
-
具体例や体験談を入れること
-
順序立てて説明すること
が重要です。
例えば、
「朝ごはんは毎日食べるべきだ」と主張したいときの本論の例:
-
理由①:集中力が上がるから
-
実際に、私(筆者)は朝ごはんを食べないで学校へ行った日は、1時間目の授業に集中できず、先生の話が頭に入らなかった経験があります。
-
-
理由②:健康にも良いから
-
家族の中学生の兄は、部活の先生から「朝食を抜くと体力が落ちる」と言われ、しっかり朝食を食べるようになりました。その結果、長距離走の記録も伸びたそうです。
-
このように、自分の体験や身近な人のエピソードを入れると、読み手に「本当にそうなんだ」と伝わり、説得力が高まります。
導入とまとめの重要性
意見文を書くとき、導入は文章の入口となる大事な部分です。
読み手の関心をひき、「なるほど、このテーマについて話すのね」と理解してもらえるように書きましょう。
たとえば、
「最近、SNSトラブルがニュースで取り上げられることが増えています。」
という一文から始めると、テーマとのつながりが自然になります。
また、まとめでは本文で述べた理由を簡単にふり返りつつ、最後にもう一度意見を強調します。
例:
「これらの理由から、私はSNSの使い方をしっかり学ぶべきだと思います。」
導入とまとめがしっかりしていると、文章全体にまとまりが生まれ、読む人に「よく考えられているな」という印象を与えることができます。
まとめると、
-
導入:テーマ提示、問題提起
-
結論:最初にはっきり書く
-
本論:理由+具体例をわかりやすく
-
まとめ:もう一度意見を強調する
この流れを意識すれば、誰でも読みやすい意見文を書くことができます。
意見文を書くためのステップ
テーマの選び方と重要性
意見文を書くとき、まず最初の大きなステップが「テーマ選び」です。
テーマがしっかりしていると、そのあとの「結論 → 理由 → 具体例」の流れがとてもスムーズになります。
テーマを選ぶときは、次のポイントを意識すると良いです。
-
自分が興味を持てること
興味のないテーマで書くと、途中で手が止まってしまいがちです。
たとえば、サッカーが好きな人なら「部活動の大切さ」、本が好きな人なら「読書の魅力」、料理が好きなら「家庭科の授業を増やすべき理由」など、自然と書きたいことが出てきます。 -
日常生活で感じたことから選ぶ
「学校のルールで変えた方がいいと思うこと」「家事を手伝うメリット」など、自分が普段から感じていることは書きやすいテーマです。
実際、小学6年生の男の子が“宿題の量について”をテーマに書いたところ、自分の体験をたくさん書けて、先生からも「説得力があるね」と褒められたそうです。 -
社会で話題になっていることを選ぶ
ニュースでよく耳にする「食品ロス」「ネットトラブル」「環境問題」なども、意見文のテーマとして人気があります。
身近な例と合わせることで、ぐっと深い意見文に仕上がります。
テーマがはっきりしていれば、読み手にも「この意見文は何について書いているのか」がすぐに伝わり、説得力が高まります。
アイデア出しのコツ
テーマが決まったら、次は「アイデア出し」です。
いきなり意見を書こうとすると手が止まりがちなので、まずは頭の中にある考えをどんどん書き出すところから始めましょう。
アイデア出しのやり方の例:
-
思いついたことをどんどんメモする
ノートに「なぜそう思うのか」「どんな体験があるか」「他の人ならどう考えるか」などを自由に書きます。
まだ文章になっていなくても大丈夫。思いついた言葉でもOKです。 -
ブレインストーミングを活用する
書きたいアイデアを気にせず、思いついた順に並べていく方法です。
中学2年生のEさんは、これを使って「校則についての意見文」を作成し、自分一人では気づけなかった観点も思い出せたそうです。 -
マインドマップで整理する
紙の中心にテーマを書き、そこから枝を伸ばして理由・体験談・解決策をつないでいく方法です。
視覚的に整理できるので、小学生にもおすすめです。
アイデアの段階でたくさん書いておけば、本番の文章を書くときに材料が多く、とても書きやすくなります。
根拠をもとにした主張の構築
意見文では「主張(結論)」だけでなく、その主張を支える「根拠」がとても大切です。
根拠がしっかりしていない意見は、どんなに立派な言い方をしても説得力が弱くなってしまいます。
根拠の作り方のポイント
-
事実やデータを使う
「朝ごはんを食べると集中力が上がる」というデータや、
「日本では食品ロスが年間◯◯万トンある」という数字は説得力があります。 -
自分の体験談を使う
実際の体験は、相手の心に届きやすい強い根拠です。
例:「私は朝ごはんを食べなかった日に授業でぼーっとしてしまった経験があります。」 -
複数の根拠を組み合わせる
データ+体験談、理由①+理由② というように複数の根拠を並べると、文章の信頼性がぐっと高まります。
たとえば、自転車ヘルメットの必要性について書いた小学生の例では、
-
事故のデータ
-
自分が転んだときに助かった体験
-
周囲の人の意見
この3つを根拠にしたことで、先生から「とてもよく考えられた意見文」と評価されました。
エピソードを盛り込んだ表現方法
意見文にエピソードを入れることで、文章に温かみが出て読みやすくなります。
また、読み手が「この子は本当にこう思っているんだ」と感じられるため、説得力が上がります。
エピソードを入れるときのポイント:
-
自分の体験を具体的に書く
「私は部活でキャプテンになった経験から、協力する大切さを学びました。」
このように、状況が具体的だと読み手も想像しやすいです。 -
短いエピソードでもOK
長い話を書く必要はありません。
たとえば、「図書館で借りた本がきっかけで歴史が好きになった」など、数行でも十分効果があります。 -
読み手の共感を意識する
「きっとみなさんも同じような経験があると思います」といった一言を入れると、読み手が親しみを感じやすくなります。
実際、小学5年生のFさんは「自分の家で飼っている犬とのエピソード」を意見文に入れたことで、クラスのみんなから「読むのが楽しかった」と言われ、自信がついたそうです。
意見文の例文とテーマ例
小学生向け意見文の例
小学生の場合、意見文は「自分の身近なテーマ」から選ぶととても書きやすくなります。
なぜなら、普段から感じていることや経験したことをそのまま文章にできるからです。
たとえば、
-
「給食の時間」
私は給食の時間をもっと長くしてほしいと思います。
なぜなら、ゆっくり食べることで健康に良いだけでなく、友だちとの会話も楽しめるからです。私は五年生のとき、給食の時間が短くて急いで食べたために、お腹が痛くなってしまったことがあります。
その日は午後の授業に集中できず、とてもつらかったです。
また、同じクラスの友だちも「もう少しゆっくり食べたい」とよく言っています。ゆっくりした時間があれば、みんなもっと給食を楽しむことができ、残さず食べられるようになると思います。
だから、私は給食の時間を長くしてほしいです。
-
「ペットを飼うことに賛成」
私は、家庭でペットを飼うことに賛成です。
その理由は、命の大切さを学べるからです。実際に、私の家では小学生のときから犬を飼っています。
毎日散歩をしたり、病院に連れて行ったりする中で、「生き物を育てる責任」を学ぶことができました。
ペットはかわいいだけではなく、お世話をすることで成長できる存在だと思います。このように、ペットは家族みんなに良い影響を与えてくれます。
だから、私はペットを飼うことに賛成です。
-
「朝ごはんは必ず食べるべき」
私は、朝ごはんは必ず食べるべきだと思います。
理由は、勉強に集中できるようになるからです。私は朝ごはんを食べないまま学校へ行った日、1時間目の授業で頭がぼーっとしてしまいました。
その日はテストで思うように力が出せず、とても後悔しました。朝ごはんは体や頭をしっかり働かせるために大切だと感じました。
だから、私は朝ごはんを毎日食べるべきだと思います。
-
「校庭にもっと木を植えてほしい」
私は校庭にもっと木を植えてほしいです。
理由は、休み時間をもっと気持ちよく過ごせるようになるからです。木の下は日かげになり、夏でも涼しく過ごせます。
私は木の下で読書するのが好きで、友だちとおしゃべりをする場所としてもぴったりです。
校庭に木が増えれば、みんながくつろげる場所が増えると思います。だから、校庭にもっと木を植えてほしいです。
など、毎日接しているものや、学校生活で気になったことは意見文にぴったりです。
また、自分の体験と結びつけて書くと、説得力のある文章になります。
小学生のGくんは、「校庭にもっと木を植えてほしい」というテーマで書きました。
その理由として「木の下で友達と本を読むのが好きだから」など、自分の経験を入れたところ、先生から「わかりやすくて良い意見だね」と褒められたそうです。
以下に例文をより詳しく紹介します。
小学生向け例文(テーマ 給食の時間を長くしてほしい)
私は給食の時間をもっと長くしてほしいと思います。
なぜなら、友だちと話しながら食べると楽しいし、ゆっくり食べることで健康にも良いからです。
実際に私は、五年生のときに時間が足りず、急いで食べてしまい、お腹が痛くなってしまったことがあります。
その日は午後の授業に集中できず、先生に「どうしたの?」と心配されてしまいました。
また、同じクラスの友だちも「もっとゆっくり食べたい」と言っていました。
みんなが落ち着いて食べられる時間があれば、食べ残しも減り、給食をもっと楽しめると思います。
だから、私は給食の時間を長くしてほしいです。
中学生向け意見文のテーマ例
中学生になると、自分の生活だけでなく社会全体に目を向ける機会が増えていきます。
そのため、意見文のテーマもより幅広く、深いものになっていきます。
中学生に人気のテーマは、次のようなものがあります。
■ スマートフォンの使い方
SNSのトラブル、時間管理、依存の問題など、身近でありながら考えるポイントが多いテーマです。
実際に「スマホの使いすぎで睡眠時間が減った」という体験を書く人も多いです。
私は、スマートフォンの使用時間を見直すべきだと考えます。
理由は、勉強や睡眠への悪影響が大きいからです。
実際に私は、夜スマホを見すぎて寝る時間が遅くなり、翌日の授業で集中できなかった経験があります。
また、SNSの通知が気になって勉強が中断されることもありました。
スマホは便利ですが、使い方を間違えると生活の質が下がってしまいます。
使用時間を決めることで、より良い生活が送れると考えます。
だから、スマートフォンの使用時間を見直すべきです。
■ 制服は必要か
制服があることで「生活にメリハリがつく」という意見もあれば、「自由に服を選びたい」という意見もあり、人によって考え方が分かれるテーマです。
私は制服は必要だと考えています。
理由は、身だしなみの差によるトラブルを防げるからです。
私の学校では、自由服の日に「何を着ていくか」で悩む人が多く、中には服装を理由にからかわれる人もいました。
制服があると、その心配がなくなるだけでなく、学校生活にメリハリがつきます。
制服は「学校に来るスイッチ」にもなりますし、みんなが平等な気持ちで過ごせる環境づくりに役立つと思います。
だから、私は制服は必要だと考えています。
■ 部活動の時間を短くすべきか
部活の負担や勉強との両立など、中学生ならではの課題が書きやすいテーマです。
「遅い時間までの練習で疲れが取れなかった」という実体験を入れると説得力が上がります。
私は、部活動の時間を今より短くするべきだと思います。
理由は、勉強との両立が難しくなっているからです。
私の友だちは、毎日19時ごろまで練習があり、家に帰ってから宿題が終わらず苦労していました。
その結果、テスト前でも勉強時間が取れず、成績が下がってしまいました。
部活動は大切ですが、長すぎる練習は生活に負担をかけます。
短くすることで、より集中して練習でき、生活全体が良くなると思います。
だから、私は部活動の時間を短くすべきだと考えます。
■ ネットいじめをなくすには
実際にニュースにも多く取り上げられ、社会問題として大きく扱われています。
「自分が見たこと」「学校で行われている取り組み」などを書けます。
私はネットいじめをなくすために、大人と子どもが協力すべきだと思います。
理由は、子どもだけでは対応しきれない問題が多いからです。
実際に、私のクラスでSNSでの悪口が問題になったことがあります。
そのとき担任の先生や保護者が間に入り、話し合いの場を作ってくれたことで、やっと解決につながりました。
ネットいじめは画面の向こうで誰かを深く傷つけています。
大人と連携しながら対策することが必要だと感じました。
だから、ネットいじめをなくすには大人と子どもの協力が必要です。
意見文を書いた作品の紹介
意見文を書くときには、実際に他の人が書いた作品を読むこともとても参考になります。
「こんな書き方があるんだ」「こんなふうにまとめればいいんだ」と、新しい気づきが得られます。
■ 学校の作文コンクール作品
学校で選ばれた作品は、主張が分かりやすく、構成もしっかりしています。
特に入賞作品には、読み手を引きつける工夫や具体例の入れ方など、学べる点がたくさんあります。
■ 図書館やインターネットで読める意見文集
図書館には「子どもの作文集」や「意見文の書き方」などの本が置かれています。
中には、実際の小学生・中学生が書いた意見文がまとめられている本もあり、「こんなふうに書ければいいんだ」と目標にできます。
■ 友だちや先輩の意見文を参考にする
自分と同じ学年の友だちが書いた文章は、レベル感が近いので参考にしやすいです。
また、先輩の作品は構成がしっかりしていて、学べる部分が多くあります。
実際にHさん(中1)は、先輩の意見文を読むことで「まとめ方のコツ」がわかり、学校の課題で高評価をもらったそうです。
意見文を書く際のチェックポイント
内容の論理性を確認する方法
意見文を書くうえでとても大切なのが、「文章の流れがしっかりしているかどうか」です。
自分ではきちんと説明したつもりでも、読み手からすると「何が言いたいのかな?」と感じることがあります。
そこで役に立つのが、次のチェックです。
■ 主張 → 理由 → 具体例 → まとめ の順番を確認する
これは、意見文の“黄金ルール”ともいえる流れです。
この順番になっているだけで、読み手は内容をスムーズに理解できます。
例:「私は朝ごはんを毎日食べるべきだと思います。(主張)
→ なぜなら授業に集中できるからです。(理由)
→ 実際に私は朝食を抜いた日に集中力が落ちた経験があります。(具体例)
→ だから朝ごはんは大切だと思います。(まとめ)」
■ 理由や根拠があいまいになっていないか
たとえば、「楽しいから」「大変だから」など抽象的な理由だけだと説得力が弱くなります。
「なぜ楽しいのか」「どう大変なのか」を丁寧に説明できると論理的になります。
■ 声に出して読んでみる
声に出して読むと、「言い回しが変」「急に話が飛んだ」といった“論理のズレ”に気づきやすくなります。
実際に、ある中学1年生の生徒は、音読したことで「理由が2つあるのに、1つ目と2つ目が逆の内容になっていた」と気づき、提出前に修正できたそうです。
読み手への伝わり方の工夫
意見文は「自分が書きたいこと」だけでなく、「相手にどう伝わるか」を考えながら書くことが大切です。
■ わかりやすい言葉を使う
難しい言葉や専門用語を多く使うと、読み手がついていけなくなります。
たとえば「学習効率が向上する」よりも「勉強がはかどる」の方が読みやすいですよね。
実際、小学6年生のHさんは「語彙力を上昇させる」と書いて先生から「少し難しい」と言われ、「言葉を増やせる」に書き直したら評価が上がったそうです。
■ 段落ごとに内容をまとめる
ひとつの段落に、理由も具体例も結論も全部書いてしまうと読みづらくなります。
段落ごとに話題を分けることで、読み手はぐっと理解しやすくなります。
■ 読み手の立場で考える
「相手はどんな知識を持っているか」「どこを説明すればわかりやすいか」を想像しましょう。
たとえば、家族と話すときも、お母さんには説明しても弟には伝わっていないことがありますよね。
それと同じで、「この説明で伝わるかな?」と考えることが文章の質を高めます。
先生からの評価を得るためのポイント
意見文は「主張が正しければそれで終わり」ではありません。
先生は文章全体の完成度も見ています。
高い評価をもらうためには、次の点が重要です。
■ 意見・理由・構成が明確か
「主張は何?」「理由はどこ?」「具体例は本当に根拠になっている?」という視点で見直しましょう。
先生は「論理的に書けているか」を特に重視します。
■ 誤字脱字をチェックする
意見がどれだけ素晴らしくても、誤字が多いと評価は下がります。
特に「見直し」は一番忘れられがちなステップです。
実際に、小学5年生のIさんは、内容は完璧だったのに小さな誤字が3ヶ所あって、点数を少し落としてしまったそうです。
ほんの5分の見直しで変わったかもしれません。
■ 原稿用紙の使い方を守る
段落の最初は1マスあける、句読点を1マスに書く、名前欄の書き方など、基本的なルールを守ることも評価につながります。
特に作文コンクールでは、形式の乱れが減点につながりやすいです。
■ 最後にもう一度読み返す
提出前の見直しで、「理由が少し弱い」「主張とまとめがずれている」といった問題に気づけます。
意見文作成に役立つオンラインリソース
無料で利用できる意見文講座
インターネット上には、小学生・中学生向けの意見文講座がたくさんあります。
動画やスライドでわかりやすく解説してくれるサイトも多く、無料で利用できるものも豊富です。
自宅で好きな時間に学べるので、苦手な部分を何度も見直すことができます。
学校の授業だけでは物足りない人や、もっと上手になりたい人におすすめです。
- NHK for School(動画で学べる)
- 学習プリントサイト(無料ダウンロード)
- 教育系YouTubeチャンネル
役立つ過去問の活用法
過去の入試問題や作文コンクールの課題を使って練習するのも効果的です。
実際に出題されたテーマで意見文を書いてみることで、実践力が身につきます。
また、模範解答や優秀作品を読むことで、構成や表現の工夫を学ぶことができます。
過去問は学校や図書館、インターネットで手に入ります。
- 入試やコンクールの過去問を使う
- 模範解答を参考にする
- 自分の意見文と比べてみる
学年別の勉強法と対策
学年によって意見文の書き方や求められる内容が少しずつ異なります。
小学生は「主張→理由→具体例→まとめ」の基本型をしっかり身につけることが大切です。
中学生は、社会的なテーマや複数の視点を取り入れる練習をしましょう。
学年に合った教材や練習問題を使うことで、無理なくレベルアップできます。
| 学年 | 勉強法・対策 |
|---|---|
| 小学生 | 基本の型を覚える・身近なテーマで練習 |
| 中学生 | 社会的テーマ・複数視点・過去問活用 |
意見文を書く際のよくある悩みとその対策
時間がない時の効率的な方法
意見文を書く時間が十分にないとき、焦ってしまい、かえって書けなくなることがありますよね。
そんなときに役立つのが「構成メモ」をつくることです。
まずは、文章にしなくても良いので、
-
結論(主張)
-
理由
-
具体例
-
最後のまとめ
この4つだけを箇条書きでメモしましょう。
たとえば「図書室をもっと利用しやすくしてほしい」というテーマの場合、
-
結論:図書室をもっと使いやすくしてほしい
-
理由①:本が好きな人が多いのに利用時間が短い
-
理由②:静かに勉強できる場所が必要
-
具体例:放課後に借りたいのに閉まっていて困ったことがある
-
まとめ:みんなが気持ちよく使える環境が大切
というように、短い言葉だけでOKです。
このメモをもとに短い文章を作れば、5〜10分でも意見文の形になります。
実際に、小学6年生のJさんは、テスト前に時間がなくてもこの方法で見事に意見文を仕上げ、「短時間でもまとまっていてすごい!」と先生に褒められたそうです。
また、文章を書いている途中で不要な説明が出てきたら、思い切ってカットすることも大切です。
時間がないときほど、“大事な部分だけを書く”ことを意識しましょう。
-
構成メモを先に作る
-
大切なポイントだけを書く
-
最後に全体の流れを見直す
これだけで、効率よくまとまった意見文になります。
苦手克服のための練習法
意見文が苦手だと感じている人は、とても多いです。
「何を書いていいかわからない」「理由が思いつかない」という悩みもよく聞きます。
そんなときは、まず 短い意見文 から練習してみるのがおすすめです。
たとえば、
私は朝ごはんを食べたほうがいいと思います。
その理由は、集中できるからです。
このように、たった2文でも立派な意見文の形になっています。
最初から長文を書かなくて大丈夫です。
さらに、家族や友だちと「意見を言い合う練習」もとても効果的です。
例えばごはんのときに
「体育の授業は週に何回が良いと思う?」
と質問し合うと、自然に理由を考える力が育ちます。
中学生のKさんは、友だちと“学校のルールについて語り合う”機会が増えたことで、意見文がどんどん書けるようになったそうです。
「話すと考えが整理される」という良い効果があるんですね。
苦手克服のポイントは、
-
短い意見文からスタート
-
家族や友だちと意見交換をする
-
1日5分でもいいから続けてみる
この3つを習慣にすることです。
モチベーションを保つための応援方法
意見文を書くときに「やる気が出ない…」ということもよくあります。
そんなときは、モチベーションを保つための工夫をすると、書くのが楽しくなります。
■ 小さな目標を決める
たとえば、
「今日は5行だけ書く」「理由を一つだけ考える」
など、小さな目標でOKです。
できたら自分に“ごほうび”をあげるのも良い方法です。
中学2年生のLさんは「作文を仕上げたらアイスを食べる」と決めて、楽しく続けられたと言っていました。
■ 書いた意見文を誰かに読んでもらう
家族や友だち、先生が読んでくれると、良いところを褒めてもらえたり、改善点を教えてもらえたりします。
「誰かが読んでくれる」と思うと、やる気もアップします。
■ コンクールや発表会に挑戦する
学校や地域で行われている作文コンクールに応募すると、目標がはっきりしてモチベーションが大きく上がります。
実際に、作文コンクールに出したことで自信がつき、その後作文が得意になった生徒もたくさんいます。
■ 書いた意見文をファイルにまとめる
自分の成長が目に見えると、やる気が続きます。
書いた文章をファイルやノートにまとめておくと、「前よりうまく書けてる!」と実感できて嬉しくなります。
意見文の書き方の復習
意見文は「主張→理由→具体例→まとめ」の流れで書くのが基本です。
テーマ選びやアイデア出し、根拠の示し方、エピソードの使い方など、ポイントを押さえて練習しましょう。
書いた後は、論理性や伝わりやすさをチェックすることも大切です。
何度も書いて、少しずつ上達を目指しましょう。
- 基本の構成を守る
- 理由や具体例をしっかり書く
- 見直しを忘れずに
将来の成長につながる意見文の価値
意見文を書く力は、将来の学習や社会生活でも大きな武器になります。
自分の考えを整理し、相手に伝える力は、どんな場面でも役立ちます。
小学生・中学生のうちから意見文に取り組むことで、論理的思考力や表現力が自然と身につきます。
自信を持ってチャレンジしましょう。
- 論理的思考力が身につく
- 表現力がアップする
- 将来の自信につながる
次に挑むためのステップアップガイド
意見文が書けるようになったら、次はより難しいテーマや長い文章にも挑戦してみましょう。
他の人の意見文を読んで学んだり、ディベートや小論文にもチャレンジするのもおすすめです。
自分の成長を感じながら、どんどん新しいことに挑戦していきましょう!
- 難しいテーマに挑戦する
- 他の人の意見文を読んで学ぶ
- ディベートや小論文にもチャレンジ
小学生・中学生必見!意見文の書き方完全ガイド!まとめ
意見文は、自分の考えを読み手にわかりやすく伝える文章です。コツをつかめば、だれでもスムーズに書けるようになります。まず大切なのは「何について、どんな意見を伝えたいのか」をはっきりさせることです。テーマが決まったら、結論を先に言う「私は○○だと思います」から始めると、読み手にとって理解しやすくなります。
次に、意見に対する理由を具体的に示します。「なぜなら〜だからです」と理由を書くことで、文章に説得力が生まれます。このとき、できるだけ自分の体験を入れたり、身近な出来事を例として取り上げると、読み手にもイメージが伝わりやすくなります。たとえば「朝読書が大事だと思います。なぜなら、集中力が高まると感じたからです。実際に私は毎日10分の読書を続けたことで、授業中の理解が深まった経験があります。」というように、体験談があるとより魅力的になります。
また、文章を書く順番を意識すると、より読みやすくなります。おすすめの流れは「結論→理由→具体例→まとめ」です。この4つだけをメモに書き出してから文章にすれば、時間がない時でもスムーズに意見文が完成します。作文が苦手な場合も、この型に沿うだけでまとまりやすくなるでしょう。
さらに、仕上げとして文章全体を読み返すことも大切です。同じ表現を繰り返していないか、主語と述語のつながりがおかしくないかなどを確認しましょう。余計な言い回しがあれば、思い切って削るとすっきりした文章になります。
意見文は「うまく書こう」と思いすぎず、自分の感じたことを素直に言葉にすることが一番のコツです。短い文章から練習したり、身近なテーマを選んだりすると、どんどん書きやすくなります。ぜひこのガイドを参考に、あなたの考えをしっかり伝える素敵な意見文を書いてみてくださいね。