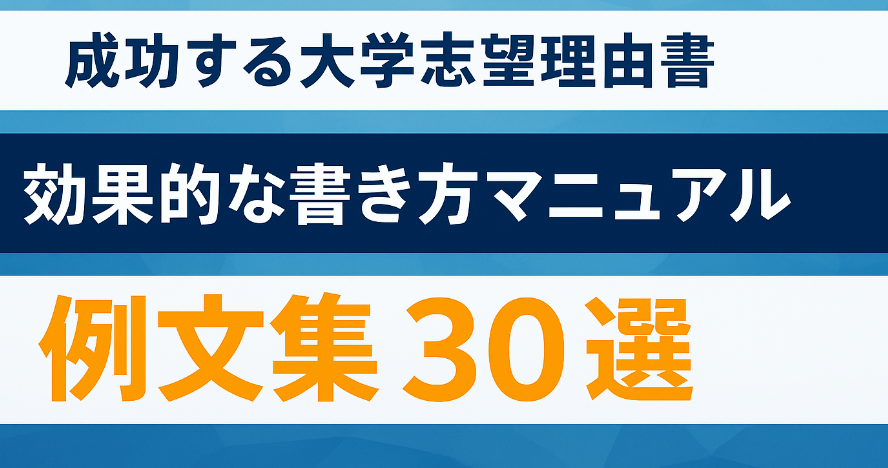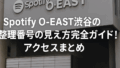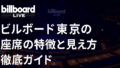この記事は、大学受験や進学を目指す高校生や保護者、または転職や進学を考えている社会人の方に向けて書かれています。
「志望理由書 書き方 例文」で検索した方が、志望理由書の基本から具体的な書き方、例文、注意点までを網羅的に理解できるよう、わかりやすく解説します。
この記事を読むことで、志望理由書の作成に自信を持ち、合格や採用に一歩近づくことができるでしょう。
大学志望理由書とは?基本を押さえよう
志望理由書は、大学入試や就職活動、転職活動などで、自分の考えや目標をしっかり伝えるためのとても大切な書類です。
「自己紹介文」と思われがちですが、実はそれ以上の役割があります。
たとえば、「なぜこの大学を選んだのか」「将来どんな仕事がしたいのか」「自分の経験がどう学びにつながるのか」などを、選考担当者が納得できるように書く必要があります。
志望理由書は、あなたの熱意・適性・将来性をアピールする絶好のチャンスです。
まずは基本をしっかり押さえておくことが、良い志望理由書を書く第一歩になります。
志望理由書の定義と目的
志望理由書とは、志望する大学に対して「自分がその大学で学びたい理由」や「将来のビジョン」を伝えるための文書です。
形式ばった文章ではなく、あなたの価値観や思い、これまでの経験が感じられる内容が大切になります。
たとえば、高校時代にボランティア活動に力を入れた人が「その経験から福祉分野に興味を持ち、もっと専門的に学びたい」と説明すれば、選考者はあなたの行動と志望動機が結びついていることを理解できます。
目的はただひとつ。
あなたの魅力を読み手に「この学生を迎えたい」と思ってもらうこと。
そのために、
-
自分の志望動機を明確に伝える
-
将来の目標やビジョンを示す
-
他の応募者との差別化を図る
といった点が重要になります。
大学入試における志望理由書の役割
大学入試では、志望理由書は「あなたの人柄や熱意を知るための重要な資料」として活用されます。
特に、総合型選抜(AO入試)や学校推薦型選抜では、学力試験以上に志望理由書が重視されることも多いんです。
たとえば、ある受験生は「中学生のときに地域のパンフレット作りに参加した経験から、デザインや情報発信の重要性に気づいた」ことをきっかけに、メディア学科を志望したそうです。
このエピソードが担当者の心に響き、面接でもその話題が深掘りされ、結果として合格につながりました。
志望理由書は、
-
学力以外の意欲や人間性を評価する材料
-
面接での質問内容のベース
-
将来の適性や目標を知るための判断基準
として、大きな役割を果たします。
志望理由書が評価されるポイント
高く評価される志望理由書には、いくつかの共通点があります。
まず“一番大切なのは具体性”。
あなた自身の体験や、そこから得た学びがしっかり書かれていると、担当者は「この学生は本当にこの分野に興味があるんだな」と感じます。
ある受験生は、祖母の介護を手伝った経験から看護学科を志望しましたが、「ただ介護が大変だった」というだけでなく、
「呼吸器の管理について学んだ際に、医療の知識がもっとあれば安心して支えられたのではないかと感じた」
という具体的な気づきを書き、説得力のある志望理由書に仕上げました。
また、文章にはその人らしさや独自性が表れるものです。
同じ学部を志望する受験生が多い中で、自分ならではの視点があると印象に残りやすくなります。
評価されるポイントは下記の通りです。
| 評価ポイント | 具体例 |
|---|---|
| 具体性 | 自分の体験やエピソードを交える |
| 独自性 | 他の人にはない視点や経験を書く |
| 将来性 | 明確な目標やビジョンを示す |
| 論理性 | 筋道立てて、分かりやすく書く |
「体験 → 興味を持った理由 → 大学で学びたいこと → 将来どう生かしたいか」という流れがしっかりしていると、読む人にも伝わりやすくなります。
志望理由書の書き方!基本ルールとは?
志望理由書を書くときには、いくつかの「基本ルール」を意識することで、一気に読みやすく説得力のある文章になります。
特に大切なのは、構成の流れをきちんと作ることと、あなた自身の経験をうまく織り込むことです。
まず、志望理由書は「導入・本論・結論」の三部構成が基本です。これは、読み手が内容を理解しやすくなる最も王道の形です。
書き出しで興味を引き、本文で具体的な理由や経験を述べ、最後に将来の意気込みで締めると、自然とまとまりのある志望理由書に仕上がります。
実際、過去に総合型選抜で合格した高校生の中には、「最初の書き出しを工夫したら、面接官が興味を持ってくれた」と話す人もいます。
文章の印象は、最初の数行で大きく変わるものなんです。
志望理由書の構成の基本
志望理由書は一般的に 導入 → 本論 → 結論 の流れで書きます。
このシンプルな枠組みに沿うことで、あなたの思いや経験が整理され、読み手にもスッと伝わるようになります。
●導入 興味を持ったきっかけ
まずは「なぜこの学部に興味を持ったのか」を簡潔に示します。
たとえば、ある受験生は「中学生の頃に見たドキュメンタリー番組が医療への興味の始まりだった」と書きました。
最初に“きっかけ”が示されると読者は自然と続きを読みたくなります。
●本論 具体的な経験や学びたい内容
次に、自分の経験や取り組んできたことをもとに「この学部で何を学びたいのか」を書きます。
実際に、ボランティア活動で高齢者と接する中で福祉分野に興味を持ち、それを志望理由につなげた学生もいました。
こうした体験は、文章に深みを与え、あなたの熱意を強くアピールできます。
●結論 将来の目標や意気込み
最後は、「この大学でどう成長したいか」「将来どう社会に貢献したいか」をまとめます。
ここが曖昧だと説得力が弱くなってしまうので注意が必要です。
この三部構成を意識するだけで、読みやすく筋の通った志望理由書に整います。
志望理由書の具体的な書き出しテクニック
書き出しは、志望理由書の中でも特に大切な部分です。
読み手の興味を引くような“自分だけのエピソード”があると、グッと印象に残ります。
●体験談やエピソードを活用
たとえば、
「私は小学生の頃から環境問題に関心があり…」
「高校の生物の授業で遺伝学を学んだことがきっかけで…」
など、具体的な出来事から書き始めると自然に文章へ引き込む力が生まれます。
実際、ある高校生は「祖母の入院をきっかけに、医療職への興味が深まった」という経験を最初に書いたところ、面接でその話題が中心になり、スムーズに話せたと話していました。
●社会問題や時事ネタを取り入れる
「少子高齢化が進む中、福祉の重要性を強く感じて…」
といった書き方も効果的です。
ニュースへの関心の高さが伝わり、志望分野への意識の深さをアピールできます。
●簡潔で明確な表現を使う
書き出しで長く語りすぎると読みにくくなってしまいます。
一文は適度に短く、分かりやすくまとめましょう。
自己分析を活用した内容作成法
志望理由書の説得力を大きく左右するのが「自己分析」です。
自分について深く理解できているほど、自然と一貫性のある志望理由になります。
●自分の強みや価値観を明確にする
「人の話を丁寧に聞くことが得意」
「新しいことに挑戦するのが好き」
など、あなたの個性が何かをまず整理してみましょう。
●過去の経験を振り返る
学校での活動、部活、アルバイト、家族との関わりなど、どんな小さな経験でも構いません。
そこから得た気づきが志望動機につながることがあります。
たとえば、ある受験生は「部活動で後輩を指導した経験から教育分野に興味を持った」と書き、非常に高い評価を受けました。
●将来の目標と現在の自分を結びつける
「将来こうなりたい」という思いと、自分の過去の経験や現在の姿がつながっていると、文章に説得力が生まれます。
単なる“夢や憧れ”ではなく、実際の行動が伴っていることが重要です。
効果的な志望理由書の具体例集
志望理由書をよりよいものに仕上げるには、実際の例文を参考にしながら、自分の経験や興味を整理することがとても役立ちます。
ここでは学部別や文字数別の具体的なポイントを紹介し、成功する志望動機の書き方も詳しく解説します。
「どう書けばいいのかわからない…」という方でも、例文を読むことで、自分の志望理由書に何を盛り込めば良いかが自然と見えてくるはずです。
学部別の志望理由書例文
学部ごとに求められる人物像や評価されるポイントが違うため、自分の志望する学部の特徴をしっかり理解することが大切です。
たとえば法学部を志望したある高校生は、地域のボランティア活動で困っている高齢者を手伝った経験から、「社会を守る仕組み」に興味を持ちました。
その経験を書いたことで、社会正義への関心が自然に伝わり、面接でもその話題で会話が広がったそうです。
経済学部を志望する学生の中には、高校の班活動で「模擬企業プロジェクト」に参加した経験を志望理由に書く人もいます。
「商品の価格設定を変えたら売上がどう変わるのか」など、数値を使って分析した経験があれば、それは立派な志望動機の材料になります。
理学部志望の学生なら、科学部での実験の成功や失敗体験が強いアピールになります。
「失敗しても原因を調べて再挑戦した経験」があると、探究心がある人物として高く評価されます。
文学部を目指す学生であれば、読書が好きなだけでなく、「特定の作家の文章表現に影響を受けた」「文章を書くことで自己表現ができた」という具体的な経験を入れると説得力が増します。
以下に、学部ごとのポイントをまとめました。
| 学部 | 例文のポイント |
|---|---|
| 法学部 | 社会正義や法律の役割に関心があることを強調。地域活動などの経験を書くと◎ |
| 経済学部 | 経済の仕組みへの興味、データ分析の経験、模擬経営などの学びをアピール |
| 理学部 | 実験経験や科学的探究心、課題発見→検証の流れを具体的に書く |
| 文学部 | 読書体験や表現の楽しさを語る。文章作成や感想文の経験が強い材料に |
大学志望理由書 800字と400字の具体例
志望理由書は文字数によって書き方のコツが大きく異なります。
実際、同じ志望動機でも400字と800字では内容の深さや表現が変わってきます。
●800字の場合
800字の志望理由書は、導入・本論・結論をしっかり展開し、自分の経験や将来の目標まで丁寧に書き込むことができます。
たとえば、
-
小学生の頃の原体験
-
中学・高校での活動
-
なぜその学部で学びたいのか
-
将来どんな職業に就きたいのか
などを流れとして書くと、読み応えのある文章に仕上がります。
ある高校生は、柔道部でキャプテンを務め、ケガをした経験をきっかけにリハビリの重要性を知り、理学療法士を目指すことにしました。
800字では、練習中のケガの状況、リハビリの大変さ、支えてくれた人の存在、将来の夢までを自然な流れで書くことができます。
●400字の場合
400字の志望理由書では、伝える内容を「最も大切な部分」に絞り込むことが必要です。
「きっかけ → 志望動機 → 将来の目標」を端的にまとめましょう。
例えば、
「高校の授業で環境問題について学び、気候変動について深く考えるようになったこと」
をきっかけとして書き、
「大学でさらに調査方法を学びたい」
という結び方をすると、短い文字数でもすっきりとまとまります。
文字数ごとのポイントは以下の通りです。
| 文字数 | 構成ポイント |
|---|---|
| 800字 | 導入・本論・結論を丁寧に。エピソードや目標まで詳しく書く |
| 400字 | 要点を絞り、志望動機と目標を簡潔にまとめる |
成功するための志望動機のアプローチ
志望理由書で特に大切なのは、「なぜこの大学なのか」が明確に伝わることです。
ただ「興味があります」「学びたいです」と書くだけでは弱く、多くの受験生と差別化ができません。
●大学や学部の特徴をしっかり調べる
オープンキャンパスでの印象や模擬授業の内容も立派な志望動機になります。
実際、ある学生は「オープンキャンパスで学生スタッフの雰囲気がよく、この環境で学びたいと思った」ことを志望理由に書き、面接でその話が高く評価されました。
●自分の経験や目標と結びつける
自分の過去から現在、そして将来の目標まで“一本の線”でつながっていると、読み手に非常に伝わりやすくなります。
例えば、
「小さい頃から動物が好き → 獣医師の仕事を知る → ボランティアで保護犬を世話した → 大学で動物医療を学びたい」
という一貫した流れは、とても説得力があります。
●独自性や具体性を意識する
「何となく興味がある」ではなく、自分だけのエピソードを入れることで、他の受験生と大きく差がつきます。
成功する大学志望理由書の例文集30選
1. 法学部|社会のルールをつくる仕事に憧れて
私は中学のときに生徒会でトラブル対応を経験し、その際に「ルールが人を守る」ことを実感しました。法律を学び、将来は弱い立場の人を守れる仕事に就きたいと考え、貴学の法学部を志望します。
2. 法学部|弁護士として企業を支えたい
父が中小企業を経営しており、契約トラブルで困った経験を見てきました。企業法務に強い貴学のカリキュラムで実践的に学び、将来は企業を法的に支える弁護士を目指します。
3. 経済学部 社会の仕組みを数字で理解したい
ニュースで見る物価や景気変動に興味を持ち、統計分析にも挑戦してきました。データ分析教育が充実した貴学で、経済の仕組みを理論と実践の両面から学びたいです。
4. 経済学部|地域経済の活性化に貢献したい
地元商店街の衰退を見て「地域を助けたい」と思うようになりました。地域経済に関する研究が盛んな貴学で学び、将来は自治体や企業で地域活性に取り組みたいです。
5. 経営学部|自分の店を持つ夢を叶えたい
小学生の頃からカフェ経営に興味があり、高校では模擬店の企画を担当しました。経営学の基礎からマーケティングまで幅広く学べる貴学で、将来の開業に向けて力をつけたいです。
6. 経営学部|リーダーシップを実践的に学びたい
部活動で部長を務める中で、組織運営の難しさを感じました。貴学の実践的なプロジェクト型授業で経営を学び、組織を動かせる人材を目指します。
7. 文学部|言葉の力を深く学びたい
読書が好きで、言葉が人の心に影響を与える力に惹かれています。幅広い文学作品を研究できる貴学で、表現についての理解を深めたいと考えています。
8. 文学部|編集者になりたい
学校新聞の制作で文章の編集に興味を持ちました。貴学の出版・編集に関する授業で実践力を身につけ、将来は読者に寄り添う編集者として活躍したいです。
9. 教育学部|子どもを支える教師になりたい
小学校の頃に担任の先生に励まされた経験から、私も誰かを支える教師になりたいと思っています。実習が充実している貴学で学び、現場で役立つ力を身につけます。
10. 教育学部|特別支援教育に携わりたい
特別支援学校でのボランティア活動を通して、この分野の重要性を痛感しました。発達支援について深く学べる貴学で、専門性の高い教師を目指します。
11. 心理学部|人の心の動きを科学的に知りたい
友人の悩み相談を受けることが多く、心の仕組みに興味を持つようになりました。実験心理学や臨床心理学を学べる貴学で、心の専門家として成長したいです。
12. 心理学部|スポーツと心理をつなげたい
部活動でメンタルトレーニングの重要性を実感しました。スポーツ心理の研究が盛んな貴学で学び、将来はアスリートを支える仕事をしたいです。
13. 国際関係学部|海外と日本をつなぐ仕事がしたい
留学先で文化の違いに衝撃を受け、国際協力に興味を持ちました。国際政治から多文化理解まで学べる貴学で、将来は海外との架け橋になる人材を目指します。
14. 国際関係学部|外国語を活かして活躍したい
英語ディベート部の活動を通して、言語を使って意見を交わす楽しさに気づきました。語学教育の質が高い貴学で、実践的なコミュニケーション能力を磨きたいです。
15. 理学部(数学)|難問に挑む喜びを追求したい
数学オリンピックに挑戦し、考える楽しさを実感しました。高度な数学教育を受けられる貴学で、論理的思考力をさらに磨きたいと思います。
16. 理学部(化学)|新素材開発に携わりたい
化学実験の授業で物質の変化に魅了されました。材料化学に強い貴学で学び、未来の生活を支える新素材の開発に貢献したいです。
17. 工学部(情報)|AI技術で社会を便利にしたい
プログラミングに興味を持ち、実際にアプリ制作にも挑戦しました。AI研究が盛んな貴学で学び、未来をつくる技術者を目指します。
18. 工学部(機械)|ものづくりで社会を支えたい
ロボットコンテストで機械設計の奥深さに触れました。実践的な工学教育が魅力の貴学で、産業に貢献できる技術者になりたいです。
19. 看護学部|患者さんに寄り添える看護師になりたい
入院中の祖母を支えてくれた看護師さんに憧れました。貴学の丁寧な実習環境で学び、安心を届けられる看護師を目指します。
20. 看護学部|災害医療に携わりたい
地域の防災ボランティアに参加する中で、医療従事者の重要性を感じました。災害看護を学べる貴学で専門性の高い看護師を目指します。
21. 医学部|地域医療に貢献したい
医師不足が深刻な地域で育ち、医療の必要性を身近に感じました。貴学の地域医療プログラムで学び、地元医療に貢献できる医師を目指します。
22. 医学部|研究と臨床の両方で活躍したい
感染症の研究に興味があり、実験にも取り組んできました。貴学の研究体制で学び、医療の発展に寄与する医師になることを志望します。
23. 薬学部|薬の力で人を救いたい
家族が薬に救われた経験から、薬の効果に興味を持ちました。最新設備で学べる貴学で、薬の専門家として活躍したいです。
24. 薬学部|製薬会社で新薬開発に関わりたい
化学が得意で、新薬開発のニュースを見るたびに憧れていました。研究環境が整った貴学で学び、社会に役立つ薬を生み出したいです。
25. 芸術学部|表現を通して人を感動させたい
絵を描くことで気持ちを表現できる喜びを知りました。貴学の実践的なカリキュラムで技術と感性を磨き、表現者として成長したいです。
26. 芸術学部|デザインで地域を盛り上げたい
ポスター制作の経験から、デザインの力に魅力を感じました。地域プロジェクトが充実した貴学で、地域に寄り添うデザイナーを目指します。
27. 体育学部|スポーツ指導者になりたい
部活動で後輩を指導する中で、スポーツ指導の道に興味を持ちました。貴学の指導者育成プログラムで学び、選手を支える指導者になりたいです。
28. 体育学部|スポーツ医学に興味がある
怪我をした経験から、身体の仕組みをもっと知りたいと思いました。スポーツと医科学を学べる貴学で、スポーツ医療に携わりたいです。
29. 環境学部|自然を守る仕事をしたい
森林ボランティアの活動を通して、自然保護の大切さを実感しました。環境問題に取り組む研究が活発な貴学で学び、地球環境に貢献したいです。
30. 環境学部|再生エネルギーの研究に携わりたい
地球温暖化のニュースを見て、エネルギー問題に関心を持ちました。貴学の環境エネルギー研究で学び、持続可能な社会の実現に寄与したいです。
志望理由書の執筆プロセス
志望理由書を作成するには、準備 → 執筆 → チェックという一連の流れを丁寧に踏むことがとても大切です。
初めて書く方は少し緊張するかもしれませんが、焦らず一つずつ進めていけば、あなたの想いや熱意をしっかり伝えられる文章に仕上がります。ここでは、準備の仕方から仕上げのポイントまで、分かりやすく解説していきます。
準備段階 情報収集と自己分析
志望理由書の質を左右するのは、この「準備段階」です。ここを丁寧に行うほど、自然と説得力のある文章が書けるようになります。
志望校・学部の特徴を調べる
まずは、志望する学校や学部が「どんな学生を求めているのか」を知ることが大切です。
たとえば、ある大学の経済学部では「社会の変化に関心があり、自ら課題を見つけて学ぶ姿勢」を重視していると明記されていることがあります。
このような情報を知っておくと、志望理由書で「自分のどんな経験をアピールすればいいか」が分かりやすくなります。
◎ 実例
高校2年生のAさんは、志望校のサイトを詳しく読み、「国際的に活躍できる人材育成」というキーワードを見つけました。
そこで、自分が英語スピーチコンテストに挑戦した経験や、留学生との交流活動で感じたことを書いたところ、先生からも「説得力があるね!」と高評価をもらえたそうです。
自己分析で強みを整理する
志望理由書では、自分の強みや経験を「志望先の学びとどうつながるのか」を説明することが重要です。
自己分析は少し難しく感じるかもしれませんが、次のような方法を使うと見えてきます。
-
今まで頑張ったこと
-
周囲から褒められたこと
-
苦労したけれど乗り越えた経験
-
将来やってみたいこと
◎ 実例
Bさんは「特に大きな実績がない」と思っていましたが、振り返ると、クラスの係活動で相談役を務め、仲間が困ったときに間に入って調整した経験がありました。
これを「協調性」「課題解決力」としてまとめ、教育学部の志望理由に結びつけたところ、文章に深みが増したと喜んでいました。
執筆段階 流れと順序
準備ができたら、いよいよ文章を書き始めます。
ポイントは「導入 → 本論 → 結論」という シンプルな構成 を大切にすることです。
構成を決めてから書き始める
最初から完璧な文を書こうとすると、手が止まってしまいがちです。
まずは、大まかに以下をメモしてみましょう。
-
志望する理由のきっかけ
-
その学部で学びたいこと
-
過去の経験の中で関連するエピソード
-
将来の目標
メモができれば、書くべき内容の道筋が自然と見えてきます。
下書きを作成して内容を確認する
下書きでは、文章のつながりを気にしすぎず、思い浮かんだことを書いて構いません。
そのあとで読み返し、段落の順番や言葉遣いを整えていきます。
◎ 体験談
Cさんは最初、文章をいきなり清書しようとして時間が足りなくなっていました。
そこで先生から「まずは箇条書きで良いから流れを作ってみよう」とアドバイスを受け、下書きを何回か書き直すことで、最終的には筋の通った読みやすい志望理由書に仕上がったそうです。
具体的なエピソードや目標を盛り込む
読み手の心を動かすのは「あなたにしか書けない具体的な経験」です。
例:
✕「私は人の役に立ちたいです」
〇「中学のとき、クラスのトラブルがあった際に、仲間の話をじっくり聞き、解決に向けて話し合いを進めた経験があります」
将来の目標も入れると、文章に一貫性が生まれます。
チェックポイント 内容の確認と修正
志望理由書を書き終えたら、すぐに提出せずに、必ず一度時間を置いてから読み直すことをおすすめします。
書いた直後は気づきにくかったミスや、文章の不自然さが、少し離れて読み返すことで意外と見えてくるものです。これは多くの受験生や学生が経験しています。あなたも、ぜひこの“見直しの時間”を大切にしてくださいね。
論理的な流れになっているか確認する
志望理由書は、あなたの想いをまとめた大切な文章ですが、感情だけで書くとどうしても順序が乱れたり、伝えたいことがぼやけたりしてしまいます。そこで重要なのが、文章の流れが 自然で読みやすいかどうか です。
特に意識したい流れは次の4ステップです。
-
きっかけ
-
具体的なエピソード
-
学びたいこと・志望理由
-
将来の目標
この順番で書けているかを確認しましょう。
具体例
例えば、「医療の道を志したきっかけが家族の病気」なのに、いきなり「将来は医師になりたいです」と飛んでしまうと、読み手はついていけません。
きっかけ → その時の経験 → そこから学んだこと → その学びをどう活かしたいか
と順番に書くことで、初めて「あなたの考えが自然に伝わる文章」になります。
実体験
ある学生さんは、最初に提出した下書きが「将来の夢」から始まり、途中で「中学時代の経験」に戻るという構成になっていました。
しかし、アドバイスを受けて順番を整理しただけで、文章の説得力がグッと増し、読み手の先生からも「とても読みやすくなったね」と褒められたそうです。
誤字脱字や表現ミスを丁寧にチェック
どれだけ内容が良くても、誤字脱字があると「丁寧さに欠ける印象」を与えてしまいます。
特に志望理由書のような大切な書類では、細かなミスが評価に影響することもあります。
チェックのコツ
-
一文一文をゆっくり声に出して読む
-
漢字変換ミス(例:「興味を持ちました」が「興味を持ち増した」など)
-
文末が続けて同じになっていないか(「〜です。」が3回続くなど)
-
主語と述語がずれていないか
また、「ら抜き言葉」「話し言葉」もなるべく避けましょう。
例:「〜していく中でわかった」→「〜していく過程で理解した」
小さな例でも印象が変わる
誤字をひとつ修正するだけでも、文章全体がしっかりした印象になります。
採点者や面接官は意外と細かいところまで見ていますので、丁寧に見直すことが大切です。
第三者の意見を取り入れる
自分で読み返すだけでは気づけない部分も多くあります。
そのため、先生・友人・家族など、第三者に読んでもらうことはとてもおすすめです。
特に、志望理由書は「読み手がどう感じるか」が大きく影響する文章です。
他の人が読んで「伝わりにくい」と感じた部分は、文章の改善ポイントになります。
こんなメリットがあります
-
自分では気づけない弱点を発見できる
-
内容の説得力を第三者目線で評価してもらえる
-
表現が固すぎる/柔らかすぎるなどのバランスも見てもらえる
◎ 実例
Dさんは、自分では「分かりやすく書けた!」と思っていたそうですが、担任の先生に読んでもらったところ、
「理由の部分をもう少し詳しく書くと、より説得力が出るよ」
とアドバイスをもらいました。
その後、スポーツ大会で班長として動いた経験を書き足したことで、
「なぜこの学部に進みたいのか」がより明確になり、自信を持って提出できる志望理由書に生まれ変わったそうです。
こうした第三者のアドバイスは、文章をより良くするための大きなヒントになります。
志望理由書づくりは、未来への第一歩
志望理由書は、あなたの経験や性格、将来の想いを丁寧にまとめる大切な文章です。
時間をかけて準備し、構成を整え、そして最後にしっかり見直すことで、
あなたにしか書けない、心のこもった一枚 に仕上がります。
焦る必要はありません。
ひとつひとつ丁寧に進めていけば、必ず納得のいく志望理由書になります。
あなたの想いが読み手にまっすぐ届きますように。
応援しています。
志望理由書の締めくくり
志望理由書の締めくくりは、読み手に強い印象を残すための重要なパートです。
ここで自分の熱意や将来のビジョンを再度アピールし、志望校や企業でどのように成長したいかを明確に伝えましょう。
また、簡潔で前向きな表現を心がけることで、好印象を与えることができます。
締めくくりの工夫次第で、全体の完成度が大きく変わるため、最後まで気を抜かずに仕上げましょう。
強く印象に残る文末の書き方
文末では、志望校や企業での学びや経験を通じて、どのような人材になりたいかを明確に述べることが大切です。
「貴学で学び、将来は〇〇として社会に貢献したい」など、具体的な目標や夢を盛り込むと印象的です。
また、感謝の気持ちや意欲を表現することで、誠実さや熱意が伝わります。
最後の一文で自分の思いをしっかり伝えましょう。
- 将来の目標や夢を明確に述べる
- 感謝や意欲を表現する
- 簡潔で前向きな表現を使う
最後の締めに必要な要素
締めくくりには、志望理由書全体の要約や、志望校・企業への熱意、将来の展望などが必要です。
また、読み手に「この人と一緒に学びたい」「働きたい」と思わせるような前向きなメッセージを盛り込むことが大切です。
自分の強みや意欲を再度アピールし、全体の流れを意識してまとめましょう。
- 全体の要約
- 志望校・企業への熱意
- 将来の展望や目標
模範的な締めくくりの例
模範的な締めくくりの例としては、「貴学での学びを通じて、将来は〇〇分野で活躍し、社会に貢献したいと考えています。
このような機会をいただければ幸いです。
」などがあります。
自分の目標や意欲を簡潔にまとめ、前向きな気持ちを伝えることがポイントです。
以下に締めくくりの例文をいくつか紹介します。
- 「貴学での学びを活かし、将来は〇〇として社会に貢献したいです。」
- 「貴社の一員として成長し、貢献できるよう努力します。」
- 「このような機会をいただければ幸いです。」
成功するための準備と注意点
志望理由書を成功させるためには、書き始める前の準備と、書いている最中・書き終えたあとの注意をきちんと押さえておくことがとても大切です。
特に高校生にとっては、志望理由書を書くのは初めてのことが多く、「何から書けばいいの?」「この表現で大丈夫かな?」と不安になるものですよね。
でも大丈夫です。
基本的なルールや“やってはいけないこと”を知っておけば、大きな失敗はしっかり防げます。
さらに、他の人の意見もうまく取り入れていくことで、最初は不安だらけだった文章も、少しずつ自信の持てる志望理由書へと育っていきます。
高校生が志望理由書を作成する際の注意点
高校生が志望理由書を書くときに、まず意識したいのは 「自分と向き合うこと」と「自分の言葉で書くこと」 です。
自己分析をしっかり行う
いきなり文章を書こうとすると、手が止まってしまいやすいです。
その前に、ノートやスマホにこんな項目を書き出してみましょう。
-
今まで一番頑張ったこと(部活動・勉強・委員会・ボランティアなど)
-
その中で大変だったこと、工夫したこと
-
褒められてうれしかった経験
-
将来、どんな分野で活躍したいと思っているか
たとえば、ある高校3年生のAさんは、最初「特別な実績がない」と落ち込んでいました。
ですが、振り返ってみると、1年生のころからずっと図書委員として活動し、読み聞かせイベントの企画を続けてきた経験があることに気づきます。
これを「地道に継続する力」「人前で話す勇気」としてアピールすることで、志望理由書の内容が一気に具体的になりました。
自分の言葉で書く
インターネットや本に載っている例文は、「構成の参考」にするにはとても便利ですが、そのまま真似してしまうと、どうしてもよそ行きの文章になってしまいます。
例:
「貴学の高度で専門的な教育環境に魅力を感じ…」
という表現も、もちろん間違いではありません。
でも、普段の自分の話し方からあまりに離れていると、面接でうまく説明できなくなることもあります。
たとえば、
「オープンキャンパスで体験授業を受けたとき、先生の説明がとても分かりやすく、ここで学びたいという気持ちが強くなりました。」
といったように、自分が実際に感じたことを素直な言葉で書く方が、読み手にも「この子の言葉だな」と伝わりやすくなります。
例文の丸写しは避ける
ネットには「合格した志望理由書例」「テンプレート風の文」などがたくさんありますが、丸写しは絶対にNGです。
最近は、学校や大学側も似た表現や同じ文章パターンをすぐに見抜いてしまいます。
ある先生は、「毎年、ほとんど同じ志望理由書が数名分出てくる」と話していました。
当然、そうした文章は印象に残りにくく、評価も下がってしまいます。
例文はあくまで「こんな構成もあるんだな」というヒントとして見て、
中身はあなた自身の経験や考えで埋めていくことが大切です。
誤字脱字をチェックする
志望理由書は、「丁寧さ」も見られる大事な書類です。
漢字の間違い、「貴校」と「貴社」を書き間違える、句読点が全くない……といった状態だと、内容以前にマイナスの印象を与えてしまいます。
-
書き終えたら一度プリントや下書きを声に出して読む
-
1日置いてから再度読み返してみる
-
先生や家族にも誤字脱字だけチェックしてもらう
こうした小さなひと手間で、仕上がりの印象が大きく変わります。
ポイントまとめ
-
自己分析をしっかり行う
-
自分の言葉で書く
-
例文の丸写しは避ける
-
誤字脱字を何度もチェックする
NG行動 やってはいけないこと
志望理由書には、絶対に避けたいNG行動もあります。
ここでは代表的な例を挙げていきます。
他人の文章をコピーする
友達の志望理由書やネットの例文を、そのままコピーして提出するのは立派な「不正行為」です。
評価が下がるだけでなく、場合によっては志望そのものに悪影響を与えることもあります。
「自分の文章に自信がないから…」と不安になる気持ちはよく分かります。
でも、たとえ少し拙くても、自分で考えて書いた文章の方が、ずっと価値があります。
事実と異なる内容を書く
「ボランティア経験があります」と書いたのに、実際は1回だけしか参加していない、
「読書が趣味です」と書いたのに、最近はまったく本を読んでいない…など、
事実とかけ離れた内容を書くのもNGです。
面接で「最近読んだ本は?」「どんなボランティアでしたか?」と聞かれたとき、答えに詰まってしまいます。
それだけで、信用を失ってしまうこともあるので、背伸びをしすぎず、等身大の自分を書くことが大切です。
抽象的すぎる表現を使う
「人の役に立ちたい」「社会に貢献したい」などの言葉は、よく使われるフレーズですが、それだけだと中身のない印象になってしまいます。
NG例:
「私は将来、人の役に立てる仕事をしたいと考えています。」
より良い書き方:
「中学生のころから、病気がちな祖母の通院に付き添ってきました。
医師や看護師の方々が、祖母だけでなく家族の不安にも寄り添ってくれる姿を見て、私も医療の現場で人を支えられる仕事がしたいと考えるようになりました。」
このように「具体的なエピソード」を添えるだけで、言葉に重みが生まれます。
志望校・企業の特徴を調べない
パンフレットやホームページをほとんど見ずに、
どの学校・企業にも当てはまるような志望理由を書いてしまうのもよくある失敗です。
「御校の教育方針に共感しました。」
だけでは、「どの部分に?」「何が他と違うと感じたのか?」が伝わりません。
オープンキャンパスで見た授業、説明会で印象に残った先生の言葉、 HPに書かれていた教育方針など、その学校だからこそ書ける理由を入れることで、説得力がぐっと増します。
他者の評価を取り入れる重要性
志望理由書は、自分の考えをまとめる作業であると同時に、「読み手にどう伝わるか」 がとても大切な文章です。
だからこそ、自分ひとりで完成させようとせず、第三者の目を積極的に借りましょう。
第三者に読んでもらう
-
担任の先生
-
進路指導の先生
-
部活動の顧問
-
家族やきょうだい
-
信頼できる友人
誰かに読んでもらうだけでも、「ここは分かりやすい」「ここは少し伝わりにくいかも」といった感想がもらえます。
ある高校生のBさんは、最初に書いた志望理由書を友人に見せたところ、
「いいこと書いてるのに、経験の部分が短くてもったいないよ」と言われました。
そこで、自分が文化祭の実行委員として動いた具体的な場面を追加したところ、先生からも「とても具体的で印象に残るね」と評価が上がったそうです。
客観的な意見を取り入れる
他者の意見をもらうときは、ただ「どう?」と聞くだけでなく、
-
読んでいて分かりづらかったところはどこか
-
もっと知りたいと思った部分はどこか
を教えてもらうと、修正のヒントが見つかりやすくなります。
もちろん、すべての意見をそのまま採用する必要はありません。
「自分が伝えたいこと」を大切にしながら、参考になる部分を取り入れていくイメージでOKです。
何度も修正を重ねる
志望理由書は、一度で完璧に書けるものではありません。
むしろ、書き直すたびに少しずつ良くなっていく文章だと考えてください。
下書き → 修正 → 第三者の意見 → さらに修正
というサイクルを繰り返すことで、最初は不安だった文章も、
「これは自分の言葉で、自信を持って出せる」と思える一枚に近づいていきます。
志望理由書づくりは、あなた自身の成長にもつながる大切なプロセスです。
準備と注意点を意識しながら、少しずつ言葉を磨いていけば大丈夫。
あなたの本音と未来への想いが、志望理由書を通してしっかり伝わりますように。
無理せず、一歩ずつ進んでいきましょうね。
いかにして志望校に合格するか
志望理由書は合格への大きなカギとなりますが、面接や他の選考とも密接に関係しています。
合格者の志望理由書には共通する特徴があり、将来の展望をしっかり描くことも重要です。
ここでは、合格に近づくためのポイントを解説します。
志望理由書と面接の関係性
志望理由書の内容は、面接での質問や評価にも大きく影響します。
面接官は志望理由書をもとに質問をするため、書いた内容に一貫性を持たせ、どんな質問にも自信を持って答えられるよう準備しましょう。
また、志望理由書と面接で伝える内容が矛盾しないように注意が必要です。
- 志望理由書と面接内容の一貫性を保つ
- 志望理由書の内容を深掘りして準備する
- 想定質問に対する答えを用意する
合格者の志望理由書の特徴
合格者の志望理由書には、具体性・独自性・将来性・論理性が備わっています。
自分の経験や目標を明確にし、志望校や企業の特徴と結びつけている点が共通しています。
また、文章が簡潔で分かりやすく、熱意が伝わる内容になっていることも特徴です。
| 特徴 | 具体例 |
|---|---|
| 具体性 | 体験談やエピソードを交える |
| 独自性 | 自分だけの視点や経験を盛り込む |
| 将来性 | 明確な目標やビジョンを示す |
| 論理性 | 筋道立てて分かりやすく書く |
将来の展望を描く重要性
志望理由書では、将来の展望を具体的に描くことが重要です。
「大学で学んだことを活かして、将来は〇〇分野で活躍したい」など、明確なビジョンを示すことで、読み手に成長意欲や目標意識が伝わります。
将来の夢や目標を志望校や企業の特徴と結びつけて書くと、より説得力が増します。
- 将来の目標を明確にする
- 志望校・企業の特徴と結びつける
- 成長意欲や目標意識をアピールする
様々なパターンの志望理由書
志望理由書は大学入試だけでなく、転職や国際的な進学など、さまざまな場面で求められます。
分野や職種、目的によって求められる内容やアピールポイントが異なるため、それぞれのパターンに合わせた書き方を知っておくことが大切です。
ここでは、分野別・職種別、転職時、国際的な視点での志望理由書のポイントを解説します。
分野別・職種別の書き方
分野や職種によって、志望理由書で強調すべきポイントは異なります。
理系分野では研究や実験への興味、文系分野では論理的思考や表現力、医療系では人への貢献意欲などが重視されます。
職種別では、営業職ならコミュニケーション力、技術職なら専門知識やスキルをアピールしましょう。
自分が志望する分野や職種の特徴を理解し、それに合わせて内容を工夫することが重要です。
| 分野・職種 | アピールポイント |
|---|---|
| 理系 | 研究・実験への興味、論理的思考 |
| 文系 | 表現力、読書体験、論理的思考 |
| 医療系 | 人への貢献意欲、責任感 |
| 営業職 | コミュニケーション力、行動力 |
| 技術職 | 専門知識、スキル、探究心 |
転職時の志望理由書の書き方
転職時の志望理由書では、これまでの経験やスキルが新しい職場でどのように活かせるかを明確に伝えることが重要です。
前職での実績や学びを具体的に述べ、なぜ転職を決意したのか、そして新しい職場でどのように貢献したいのかを論理的にまとめましょう。
また、企業研究をしっかり行い、その企業ならではの魅力や共感ポイントを盛り込むと説得力が増します。
- 前職での経験や実績を具体的に述べる
- 転職理由を明確にする
- 新しい職場での目標や貢献意欲を示す
- 企業研究の成果を反映する
国際的な視点での志望理由書の重要性
グローバルな進学や就職を目指す場合、国際的な視点を持った志望理由書が求められます。
異文化理解や語学力、国際社会での活躍意欲などをアピールしましょう。
また、海外の大学や企業が重視する「多様性への理解」や「グローバルな課題への関心」も盛り込むと効果的です。
自分の経験や将来のビジョンを国際的な文脈で語ることがポイントです。
- 異文化理解や語学力をアピール
- 国際社会での活躍意欲を示す
- 多様性やグローバルな課題への関心を盛り込む
成功する大学志望理由書!効果的な書き方マニュアル、例文集30選
大学の志望理由書は、自分の想いや将来の目標を言葉にして伝える大切な書類です。最初は難しく感じるかもしれませんが、基本的なポイントさえ押さえれば、あなたらしさがしっかり伝わる魅力的な文章に仕上げることができます。このブログでは、志望理由書を書くための準備から構成の作り方、注意点、さらに実際に参考になる例文30選まで幅広く紹介しました。
まず大切なのは、自己分析と情報収集です。自分が努力してきたこと、これから挑戦したいこと、大事にしている考え方を振り返ることで、文章に芯が生まれます。また、志望校や学部の特徴、求める人物像を知ることで、より説得力のある志望理由に繋がります。
文章を書くときは「きっかけ → 経験 → 学びたい内容 → 将来の目標」という流れを意識すると、読み手が理解しやすい構成になります。特に、あなた自身の具体的なエピソードを盛り込むことで、印象に残る志望理由書になります。例文30選では、学部別・目的別に多様なパターンを紹介しているので、自分の書き方の参考として役立ててください。
さらに、完成度を高めるためには、見直しと第三者の意見が欠かせません。誤字脱字や表現のズレを確認したり、先生や家族に読んでもらって「もっとこうした方が伝わるよ」というアドバイスを受けることで、文章はどんどんブラッシュアップされていきます。
また、志望理由書で避けるべきNG行動についても触れました。他人の文章のコピーや事実と異なる記述、抽象的すぎる表現は、読み手に不信感を抱かせたり説得力を下げてしまいます。あなた自身の言葉で、正直に、ていねいに書くことが何より大切です。
志望理由書は「未来への第一歩」。このマニュアルと例文集が、あなたの魅力がしっかり伝わる一枚を作るお手伝いになれば嬉しいです。焦らず、自分のペースで言葉を紡いでいきましょう。あなたの想いが、きっと読み手に届きますように。応援しています。